文章を書くためには、事前準備がモノを言う!
「新しい文章力の教室」に学ぶ、最後まで読んでもらえるライティング術をご紹介!
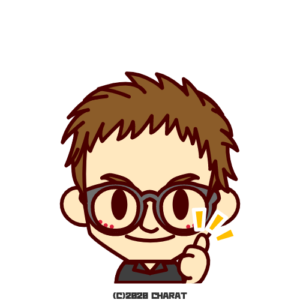
- 「内容がとっ散らかって上手に文章が書けない」
- 「書くのが遅くてブログの更新がままならない」
- 「売れる文章が書けない」
こんな悩みはありませんか?
この記事では、誰でも書けるようになる、文章を書く前の準備と売れる文章の型を「新しい文章力の教室」の中からご紹介します。
1.いきなり書き始めると失敗する

ブログなど文章を書く時には、いきなり書き始めてはいけません。
まずは、文章構成の設計図を書くことをおすすめします。
あなたはプラモデルを作るときに、プラスチックの塊だけを渡されて、作れますか?
それだけで作るのは難しいですよね。
パーツ、取扱説明書、完成図がセットになって、プラモデルを完成させることができます。
それと同じです。
文章のうまい人は適当に書かずに、しっかり準備をして書き上げます。
上手な人も下準備をして文章を書くのですから、初心者がかなうわけもありません。
設計図を作らずに文章を書いていると、とっ散らかったものとなり、誰も最後まで読んでくれることはありません。
では、どのように設計図を作ればいいのか、ご紹介していきます。
2.書く前に準備する
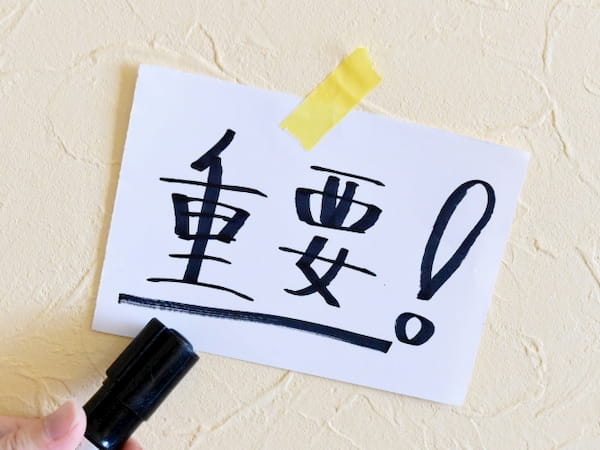
書き始める前に、テーマと道筋を決めましょう。
良い文章の目的は完読してもらうことです。
完読してもらうためには、
- 何を言うための文章なのか
- 何をどれからどのくらい話すか
ということが明確になっていることが必須条件です。
ここが定まっていると、内容が散らばることなく、まとまった文章を書くことができるようになります。
3.テーマを決める

テーマを決めるためには、書きたいことのパーツをそろえることが必要です。
書きたい内容のパーツがないことには、文章を書くことはできないからです。
なので、これから書こうとしていることの話題を箇条書きで書き出してみましょう。
この時にはとにかくドンドン出していくことが大切なので、順番とか整合性を気にしなくても良いです。
特にブログを書く時には、
- Why(なぜ)
- What(何を)
- How(どうやって)
を集めていくと、読んでいる人に伝わりやすく、有益な記事を書くことができます。
パーツが集まったら、何についての記事にするのか、テーマ(タイトル)決めましょう。
4.道筋を決める

テーマ(タイトル)が決まったら、
- 何を
- どれから
- どのくらい
書くかの道筋を決めていきましょう。
どの話題から話していくのか、順番を考えていきます。
話の順番にしっくりこなければ、何度もやり直してみましょう。
順番が決まったら、アピールしたい重要度をランク付けしていきます。
話の中で重要だと思う部分には、情報や言葉を補うことも必要です。
実際に書く時には、人に話をしているつもりで文章を作り上げていくとうまくいくと思います。
5.基本の構成は結論から伝える

分かりやすい文章の基本は「結論」から言うということです。
文章を最後まで読みたくなるように、冒頭部分で読者の興味を引くことができると、最後まで読んでもらうことができます。
ここでは特にセールスライティングをする上で、とても大事な二つの型をご紹介します。
5-1. PREP法
PREP法は結論から言い始める、とても有名な型ですね。
結論をまず伝えることで、主題を念頭に置いて話を聞くことができるので、とっ散らかることなく伝えることができます。
PREP法は以下のような順番で文章を構成していきます。
P:Point(結論)
R:Reason(理由)
E:Example(例)
P:Point(結論)
P:私は音楽が大好きです。
R:小さい時から、楽器をやってきたからです。
E:例えば、ピアノは年中さんから習っていますし、サックスも中学の時からやっています。
P:これからも大好きな音楽を続けていきたいです。
いかがでしょうか。
とても使いやすい型なので、まずはPREP法から習得してみましょう。
5-2. PASONAの法則
ブログを書いていても、なかなか収益につながらないということってありませんか?
実は、今のままブログを書いていても、一生収益をあげることができないのです。
じゃあ、どうしたらいいのか。
それは、これからご紹介するPASONAの法則を使うと一発で解決します。
これはテレビショッピングなどでよく見かける型で、相手に行動を起こしてもらいたい時によく使われる手法です。
PASONAの法則は以下のような順番で文書を構成していきます。
P:Problem(問題提起)
A:Agitation (あおり)
So:Solution(解決策)
N:Narrow Down(今すぐ行うべき理由)
A:Action(行動)
具体例(テレビショッピング)
P:30歳を過ぎて、しみやしわが気になるあなた
A:このままでは、どんどん老けていき、取り返しのつかないことになりますよ
So:そんなときはこの美容クリーム!これを使用すればマイナス10歳を若返ります!
お客様の声
N:今だけ特別ご奉仕!定価の30%offでご提供します!
A:申込は今すぐ!今から30分間オペレーターを増やしてお待ちしております
いかがでしょうか。
テレビショッピングで聞いたことのある例じゃないですか?
この型を知ったあなたは、今すぐブログのリライトをしてみてください。
早くしないと、どんどんライバルに差をつけられますよ!
6.推敲して直す
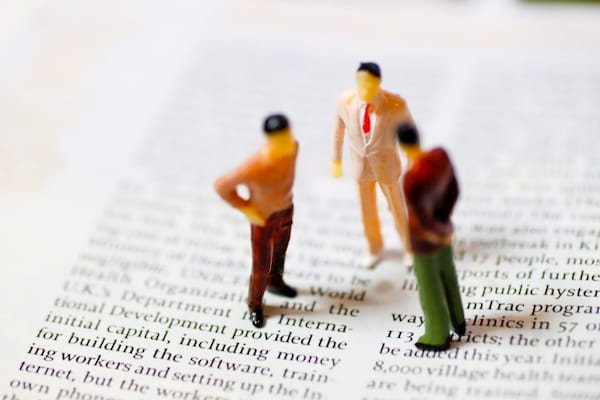
文章を書いたら、最後に誤字脱字や読者にとって読みやすい文になっているか確認する必要があります。
それを推敲と言います。
推敲をしないと、正しくない情報や読みづらい文のまま読者に届くことになるので、最後まで読んでもらうことができない可能性がアップします。
完読してもらうことが良い文章であるという定義のもとここまでお話ししてきましたので、最後まで読んでもらえないということはその文章は良い文章ではないということになります。
以下3点に気をつけて推敲をして、完読してもらう文を目指しましょう。
- 声に出して読んでみる
- 漢字が多すぎないように気をつける
- 重複表現をチェックする
6-1. 声に出して読んでみる
推敲の方法として、最も簡単なやり方は声に出して読んでみることです。
読んでみることで、助詞の誤りや誤字脱字に気付きやすくなります。
また、言葉がつっかえたり、発音しにくかったりするものは大体日本語的に誤りのことが多いです。
「ご説明させていただきます」
→させていただきますって噛みそうじゃないですか?本当は「ご説明いたします」で良いんです。
6-2. 漢字が多すぎないように気をつける
漢字が多すぎないように気をつけましょう。
漢字が多過ぎると、見た目が黒くなって、窮屈になります。
かといって、ひらがなやカタカナがおおくてもくうかんがしろくなってまぬけでようちにみえます。
なので、半分半分くらいのバランスでほどよいグレーを目指すのが良いでしょう。
6-3. 重複表現をチェックする
重複した助詞や名詞などをチェックしましょう。
よくあるのは「の」が連続することです。
私の母の勤めていた会社の上司は厳しい人です。
→私の母が勤めていた会社の上司は厳しい人です。
上の例のように3つ以上続く「の」は言い方を変えましょう。
一つを「が」に変えただけでもずいぶんと印象が変わりますね。
重複することで間延びして、長ったらしい文章になりがちなので、気をつけましょう。
7.まとめ
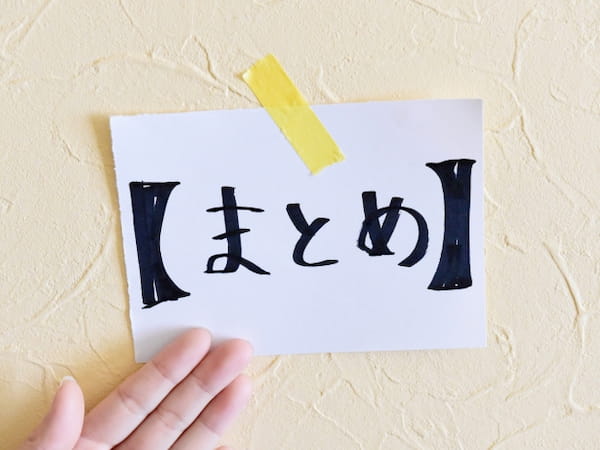
いかがだったでしょうか。
「新しい文章力の教室」では良い文章とは最後まで読んでもらえる文章という定義のもと、どうすれば完読してもらえるのかいう文章術が書かれています。
完読してもらうためには、思いつきで書くのではなく、設計図を作った上で文章を書き始めることが大切でした。
その他にもこの本の中には、さらに詳しい推敲の仕方や細かな表現方法についても書かれています。
これを読まないと基礎ができないので、いつまで経ってもうわべだけの文章を書き続けることになります。
これからブログやWebライターを目指して文章を書く方には、ぜひ読んでいただきたい一冊です。
最後までこの記事を読んでくださって、ありがとうございました!
